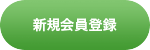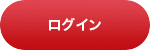お盆・初盆に贈る花2024年
2024年のお盆は、7月盆の場合は7月13日(土)〜16日(火)、8月盆の場合は8月13日(火)〜16日(金)です。
お盆や初盆の風習は、ご先祖様を大切にする日本人にとって欠かせない行事。お盆・初盆の花は、お盆入りの前に用意し、ご先祖様をお迎えする準備をととのえましょう。
現在、2024年の
お盆・初盆に向けて
特集を企画中です
お盆の花・初盆の花を贈る
お盆の期間は地域によって違いがありますが、関東や都市部では7月盆、関西や地方では8月盆が一般的とされています。お盆や初盆のご供花は、盆入り前に準備することをおすすめします。
ご供花も地域ごとに風習が違う場合があります。全国約1,200店のイーフローラ加盟生花店は、それぞれの地域に店舗を持ち、その土地の風習やマナーをよく知る花のプロ。だから、地域ごとの風習が大切なお盆や初盆、ご法事の花もご安心しておまかせください。
お線香やお菓子、飲料など、お盆・初盆に欠かせない品
お供えと一緒に花を贈る
お盆・初盆のご先祖供養の際、花と同じくらい欠かせないものが、お供えの品です。お線香やお菓子、飲料など、全国の花屋が選び抜いたお供えの品を、花と一緒に心を込めてお届けします。
-
お線香と一緒に花を贈る

お線香の煙には「仏様の食べ物」「あの世とこの世の橋渡し」「自分の身とその場を清める」などの意味があるとされています。ご法事やお参りに欠かせないお線香を、お盆・初盆の花と一緒にお贈りいただけます。
お線香と一緒に
花を贈る -
お菓子と一緒に花を贈る

ご仏壇にお供えするお盆のお菓子としては、日持ちのするおせんべいや羊羹、干菓子、クッキーなどが適しています。ご先祖様への感謝とともにお供えしましょう。
お菓子と一緒に
花を贈る -
飲料と一緒に花を贈る

お盆のお供えには、お茶や紅茶、コーヒー、ジュースといった飲料類もおすすめです。全国の花屋が、お盆・初盆の花と一緒に心を込めてお届けします。
飲料と一緒に
花を贈る -
すべてのお供え+花から選ぶ

全国の花屋が心を込めておつくりする「お盆の花とお供えの品のセット」の一覧からお選びいただけます。お贈りするお宅に合わせて選んだお供えの品は、きっと喜んでいただけます。
すべてのお供え+花
から選ぶ
地元の花屋が風習に合わせておつくりします
お盆のおまかせ商品
地域に合わせたご供花をおつくりします
お盆・初盆のご供花は、関東や関西など地域によって違いがあるもの。ご供花をお贈りする際、「こちらでは一般的なご供花だけど、あちらの地域では大丈夫かな?」という不安を感じたことはありませんか?
そんな不安を解消できるのが「お盆のおまかせ商品」です。
「お盆のおまかせ商品」は、ご供花のデザイン・制作を花屋におまかせいただくご注文方法。「地域に合わせて」「白を基調に淡く」「色とりどりに」の3つの色合いから、お届け先様に合わせてお選びいただけます。
お届け先様地域の風習に合わせて、3つの色合いからお選びいただけます

お届けする地域の風習に合わせたご供花をおつくりします

白色をメインに、淡い色の花を入れておつくりします

黄色や紫などの花を入れ、色とりどりにおつくりします
地域の風習が分からなくてもご安心ください
お届け先地域のお盆・初盆の風習をご存じない場合は「地域に合わせて」をお選びください。「お盆のおまかせ商品」のご注文をお受けするのはお届け先近くにある花屋、すなわち“その地域の風習を熟知した花屋”です。その花屋が責任をもって風習に沿ったお盆・初盆の花をおつくりし、直接手渡しで大切にお届けします。
全国の花のプロがおつくりする、安心の「お盆のおまかせ商品」。4,400円(税込)からご注文いただけます。
想いは花に、言葉はカードに
お盆・初盆の花に添える「じぶんdeカード」
お盆・初盆のご供花には、メッセージを添えてお贈りしましょう。花に込めた想いが、よりいっそう伝わります。
「じぶんdeカード」は、WEB上で簡単に制作いただけるイーフローラオリジナルの無料メッセージカード。お盆・初盆の花に添えてお贈りいただけます。
カードの制作は簡単。ご注文時にお好きなカードデザインを選び、メッセージをご入力ください。花屋がカードを印刷し、お盆・初盆の花と一緒にお届けします。
- じぶんdeカードは無料です
- プレビュー画面で見ながら簡単制作
- お供えに相応しいカードもご用意
ご希望の日・お時間にあわせて花をご用意します
お盆・初盆の花を、来店予約で

WEB上から花屋へのご来店をご予約いただくと、お約束のお時間までにご希望のフラワーギフトをご用意する便利なサービス「来店予約」。お受け取り当日にお待たせすることなく花をお渡しします。ご法事やお墓参りの日程・お時間に合わせてご予約いただければ、当日お出かけの際に花を受け取ることも可能です。
「ご供花はどんな花がいいの?」「故人が好きだった花をお供えしたい」「お墓にお供えする一対の花が欲しい」そんな疑問やご要望も、事前に花屋にご相談いただけます。
全国ネットワークのイーフローラだから、ご訪問先近くの花屋の来店予約も可能。地元の花屋ならその地域のご供花の風習に詳しいので安心です。
また、ご来店10日前からのご予約が可能です。15時までのご予約でその日のうちにご来店いただけます。
こちらから来店予約可能な花屋をお探しください
お盆・初盆のお供え花について

お墓参りのときや仏壇などにお供えする花のことを「仏花(ぶっか)」と呼びます。その中で、お盆の時期に盆棚(精霊棚)にお供えする花を特に「盆花(ぼんばな)」と呼ぶこともあります。
盆花にはご先祖様が宿るとも言われており、お盆には欠かせない供物のひとつです。仏花・盆花というと、決まり事などを難しく考えてしまうかもしれませんが、実は仏花や盆花というのは基本的には“その季節の盛りの花(時花)”を選べばよいものです。
昔のお盆では、先祖の霊は山に住むという考えから、人々はお盆の前に山へ入ってその季節の花を用意したと言われています。
仏花・盆花によく使われる菊の花
仏花や盆花としてよく使われるのが菊の花です。菊の花は、平安時代から漢方などでも優れた薬効をもつ薬草として重宝され、また観賞用としても広く親しまれてきました。和歌などにおいても盛んに引用され、天皇家の菊花紋として崇高なイメージも持っています。このように、日本人に長い間親しまれてきた菊の花が、仏花として自然と多く使われるようになったと言われています。
また、菊は花が長持ちで、枯れるときも花びらがあまり散らないため周囲を汚しにくいといったことも、仏花として選ばれやすい理由だといえます。
そして菊の花にはもうひとつ、日本で仏花として使われるようになった由来としてよく挙げられる説があります。それは、ポーランドやフランス、クロアチアといったヨーロッパ圏の一部の国においてお墓参りのときに白い菊が使われる風習があったため、日本でもその影響を受けてお葬式での献花やお供え花などに使われるようになったという説です。
地域や習慣によって違いのある盆花
同じ地域の中でも風習が違う場合もあるため一概にはいえませんが、ご供花は一般的に「海に近い地域は華やかな色合い、山に近い地域は控えめな色合い」という傾向があるようです。
菊以外の花では、盆の時期に咲く花や秋の花などがよく盆花とされます。中でも一般的な花は、夏に赤紫の花を咲かせるミソハギです。
お盆・初盆のお供え花 キキョウ、ヤマユリ、女郎花(おみなえし)、撫子(なでしこ)などの特定の花が「盆花」と呼ばれることも。また、地域によってご供花に使われる花がある程度決まっている場合もあります。京都や長崎のハス、広島県尾道のハギ、センニチコウなどがそうです。
盆棚や仏前にほおずきを飾る地域や、ハスの葉に少量の水を垂らしたものをお供えするところもあります。このハスの葉に垂らした水のことを「閼伽(あか)」と呼び、仏教では供養のために使う水が「閼伽」で、穢れを祓う水とされています。
生花を使うことの多い盆花ですが、北関東の一部などでは、金銀の紙で作られた造花の盆花をお供えする地域もあります。
お盆・初盆のご供花は
イーフローラにおまかせください
イーフローラは全国約1,200店をつなぐ「花屋ネットワーク」です

心を込めてお届けしたい。風習やマナーにきちんと沿ったお盆・初盆のご供花をお贈りしたい。そんな時は、全国花屋ネットワークのイーフローラにおまかせください。 イーフローラに加盟する花屋は、北海道から沖縄まで全国約1,200店。これらはすべて、イーフローラが定める一定の水準を満たしたプロであり、全国それぞれの地域に実店舗を持ち対面販売をしている、地域に根ざした「街のお花屋さん」です。 その地域の風習やマナーをよく知り、いざという時に頼りになる花のプロばかり。だから、地域ごとの風習が大切なお盆・初盆の花やご法事の花も安心です。地元の花屋としての強みと、全国約1,200店のネットワークを最大限に活かして、お盆・初盆の花をお届けします。
施設で行われるご法事にもお花をお届けします
お別れの会やご慰霊の会など、会館や法要式場などで行う式典にも、花屋がご供花をお届けします。式典の開始時刻、会場となる部屋を事前にご確認いただいたうえで、花屋にご相談ください。 ※法要式場によっては、外部からの花のお届け(持込み)ができない場合がございます。事前に法要式場にご確認ください。
2024年の全国各地のお盆の時期は?
関東地方など:7月13日(土)〜16日(火)
関東地方では、新暦でお盆を行う地域が多いようです。理由としては、明治5年に旧暦から新暦に切り替わった際、明治政府のあった東京やその周辺の地域、都市部などは令に従い新暦を積極的に採用し、その流れでお盆も新暦で行うようになったという説が有力です。
北海道、関西地方など:8月13日(火)〜16日(金)
新暦を基準とはするものの、旧暦のお盆になるべく合わせるために1ヶ月遅れの8月とする地域が多いようです。 理由としては、明治政府から離れた地域では、新暦が採用されたとはいえ、やはり昔からの慣習を守りたいという気運があったからと言われています。
沖縄、奄美地方など:8月16日(金)〜18日(日)
沖縄や奄美地方は、旧暦をとても重視する地域が多く、旧暦の7月13日〜15日にあたる日にお盆を行います。2024年のお盆は8月16日(金)〜18日(日)となります。沖縄では現在でもさまざまな行事を旧暦で行いますが、中でも「シチグヮチ」とも呼ばれるお盆はその代表的なもの。「家族を大切に、祖先を大切に」という考えの強い沖縄では、お盆は一年で最も大切な行事です。
お盆・初盆の花と一緒に、お供えの品もお贈りいただけます
お盆・初盆のご先祖供養の際、ご供花と同じくらい欠かせないお供えの品。お線香やお菓子など、全国の花屋が選び抜いたお供えの品を、花と一緒に心を込めてお届けします。
じぶんdeカードに綴るメッセージ 花と一緒に想いを込めた言葉を
想いは花に、言葉はカードに。お盆・初盆の花と一緒に、大切な方への想いをのせた無料メッセージカード「じぶんdeカード」もお贈りしましょう。
お盆・初盆のお話
お盆は、年に一度ご先祖様の精霊をお迎えして日頃の感謝を伝え、供養する日。日本で古くから営まれている伝統行事です。そんなお盆や初盆にまつわる、さまざまなお話をご紹介します。
お客様の声
イーフローラ加盟店の花屋にてお盆・初盆の花をご購入いただいたお客様より、毎年たくさんの声をいただいております。その一部をご紹介します。
「先日は、お盆のお忙しい中、すばらしいお花を届けて頂き、ありがとうございました。祖母の13回忌の法要でしたが、仕事で行くことが出来ず、おまかせのお花をお願いしました。すぐに『とても感激したよ。ありがとう。』と電話があり、法事に参加出来なかった申し訳ない気持ちが晴れました。値段以上のお花で、私自身、鼻が高い気分です。本当にありがとうございました」
「先程、お花のお礼の連絡が実家からあり、大変喜んで貰えました。華やかに仏壇を彩るお花を、お盆のお参りに間に合わせていただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。又ぜひ利用させていただきます」
「お盆にお花の配達をお願いいたしました。その節は大変ありがとうございました。写真を送っていただき、とてもステキなアレンジメントで感動いたしました。先方様にもとても喜んでいただきました。ご主人の新盆だったのですが、お花を見てまた新たな涙が出てしまったけれど、同時に気持ちが洗われて静かにお盆を過ごすことができたとの連絡をもらいました。これからも良いお仕事をと心からお祈りしております」
「今日、初盆の法事で届けていただいたとても立派なお花を拝見しました。おかげさまで、とても良い父の初盆を迎えることができました。本当にありがとうございました」
「昨日はお花をお届けいただきありがとうございました。お盆のお供えにぴったりの素敵なお花だと、先方からも大変喜んで連絡をもらいました。四十九日の法要の時にも利用しましたが、貴店のお花がとても喜ばれたのでまた貴店にお願いしました。初盆のお供えに一層花が添えられました」
全国の花屋がご提案するお盆・初盆の花一覧
イーフローラに加盟する全国約1,200店の花屋が、心を込めておつくりしご提案するお供え・お悔やみの商品一覧をご覧いただけます。
よくあるご質問
お盆や初盆のお花の届け日指定はできますか?
お盆期間のご希望日にお届けします。ご注文日・お支払い方法によってお届けできる日が変わりますので、お届け日をご確認のうえ、お早めのご注文をおすすめします。
急ぎの注文にも対応できますか?
朝10時までのご注文で、その日のうちにお届けします。急にお花が必要になった場合、当日の朝10時までのご注文でその日のうちにお届け可能です。
お盆・初盆にふさわしいお花の提案はしてもらえますか?
その地域の風習に詳しいお花屋さんがお花をおつくりする「お盆のおまかせ商品」をご利用ください。4,400円(税込)からご注文いただけます。※一部特別配送料を承る地域やお届けできない地域があります
手渡しお届けとは何ですか?
お届け先様のお住まい地域にあるお花屋さんがお花をおつくりし、直接手渡しでお届けする方法です。だから送料無料のお花も豊富!新鮮なお花を心を込めてお届けします。
イーフローラとはどんな会社?
イーフローラは、全国のお花屋さんが加盟する「お花屋さんネットワーク」です。全国約1,200店の加盟店がインターネットで結ばれ、全国各地に迅速に花をお届けいたします。お客様の「想い」を大切に、安心・便利な各種サービスをご提供しています。
お盆・初盆の花を贈るならイーフローラで。
便利な各種サービスや花屋の手渡しお届け(送料無料)も
お供え・お悔やみ 目的別の特集へ
-

お供えやお悔やみの花は、故人の魂を慰め、ご家族の悲しみを癒してくれるもの。全国の花屋が、心を込めてご供花をおつくりします。
-

毎年一度の「祥月命日(しょうつきめいにち)」や、毎月訪れる「月命日」があります。いずれの命日にも、ご供花は欠かせないものです。
-

ご法事は7日おきに行ない、四十九日で忌明けのご法事を行なったあと、一周忌からは年忌法要(一周忌、三回忌、七回忌など)となります。
-

通夜は、主に親族が故人の成仏をお祈りする場。告別式は、故人と関係のあった方々が葬儀において故人とお別れを告げる仏教の儀式です。
-

大切な家族であるペットをなくされた方の悲しみに寄り添い、ペットの安らかな冥福を祈るご供花をお贈りしましょう。
おすすめフラワーギフト特集
誕生日| 母の日| 父の日| 結婚記念日・ご結婚祝い| 歓送迎会・退職お祝い| 開店・開業祝い| 劇場・発表会| 恋人の日| バルーン付きの花| 入学・卒業・就職祝い| 新築・引越し祝い| 昇進・昇格祝い| ご出産祝い| お見舞い| お供え・お悔やみ| 命日| ペットのお悔やみ・お供え| お祝いスタンド花| お悔やみスタンド花| 花束| アレンジメント| プリザーブドフラワー| リース| 観葉植物| アートフラワー| 胡蝶蘭を贈る| 花たちで選ぶ| ENJOY HOME with FLOWERS(ご自宅用の花)